
EUを苛む「安定」という名の呪縛-西バルカンを覆うスタビリトクラシーの影
- 1.「スタビリトクラシー」とは何か:概念の起源と展開
- 2.EUのジレンマ:「拡大のための平和」か「平和のための拡大」か
- 3.ヴチッチ・セルビア政権に見るスタビリトクラシーの典型
- 4.地域全体に広がる民主主義の後退
- 5.「安定」がもたらす深刻な弊害
- 6.揺らぐ「安定」と今後の展望:西バルカンを待つ三つのシナリオ
- 7.偽りの安定を超えて
1990年代のユーゴスラヴィア紛争がもたらした深い傷跡と、今なお燻り続ける民族間の対立。西バルカン地域と聞いて、多くの人々が思い浮かべるのはこうした「不安定」なイメージかもしれない。特に、日頃この地域に関する報道が少ない日本では、未だに90年代の紛争のイメージが根強いと言えるだろう。
一方で、この20年以上にわたって欧州連合(EU)や米国をはじめとする西側諸国が最も重視してきたのは、まさにこの地域の「安定」であった。紛争の再発を防ぎ、地政学的な影響力を確保するという目的の下、西側諸国は西バルカン地域の指導者たちと暗黙の取引を交わしてきた。その取引こそが、今日この地域が直面する深刻な構造的問題を生み出す土壌となったのである。この問題を的確に捉えるため、近年、専門家の間で用いられるようになったのが「Stabilitocracy(スタビリトクラシー)」という概念である。
本稿では、まずこのスタビリトクラシーという分析概念の起源と学術的な展開を解説する。その上で、セルビアを中心に西バルカン全域に広がるこの体制の構造と、それを助長してきたEUの政策的ジレンマを解き明かす。そして、スタビリトクラシーが地域の民主主義と将来にどのような深刻な影響を及ぼしているのか、さらに、この構造が今どのような挑戦に直面しているのかを多角的に分析する。
(アイキャッチ画像は「平和・安定・ヴチッチ」と表記されたセルビア進歩党の選挙キャンペーン用看板、出典:Shutterstock)
1.「スタビリトクラシー」とは何か:概念の起源と展開
「スタビリトクラシー」という用語は、日本語ではまだ馴染みが薄く、専門家の間でもその認知度は限定的である。この言葉は「stability(安定)」と「autocracy(専制政治)」を組み合わせた造語であり、2016年頃から、西バルカン地域の特異な政治状況を分析する学術的文脈で注目されるようになった。それは一言で言えば、民主主義的な価値や法の支配を犠牲にする代わりに、西側諸国に対して「安定」を提供することで、国内における権威主義的な支配を正当化し、外部からの支持を取り付ける政治体制を指す。
この概念の初期の提唱者の一人とされるのが、歴史家・政治評論家のスルジャ・パヴロヴィッチ(Srđa Pavlović)である。彼は、2016年に発表したモンテネグロ政治に関する寄稿文の中で、スタビリトクラシーを「西側のパートナーが地域の権威主義的指導者の非民主的な統治、汚職、縁故主義に目を瞑る代わりに、その指導者が(しばしば見せかけの)地政学的な安定を保証するという暗黙の合意に基づくシステム」として定義した。これは、地域の指導者が西側にとっての「問題解決者」を演じることで、国内での権力乱用に対する批判を免れるという取引構造を鋭く指摘したものであった。
この概念は、西バルカン研究の第一人者であるフロリアン・ビーバー(Florian Bieber)グラーツ大学教授らによって、さらに理論的に精緻化された。ビーバーは、その著書『西バルカンにおける権威主義の台頭(The Rise of Authoritarianism in the Western Balkans)』などにおいて、スタビリトクラシーの下にある国家が「競争的権威主義」の様相を呈していると分析した。すなわち、選挙という民主主義的な手続きは存在するものの、メディアは完全に政権の統制下に置かれ、国家機関や公共部門の雇用は与党への忠誠心によって左右されるため、野党は著しく不公平な条件の下で戦うことを強いられる。その結果、公正な競争は形骸化し、実質的な政権交代は極めて困難となる。
ビーバーらが参加する南東欧研究に特化したシンクタンク「欧州におけるバルカンの政策提言グループ(Balkans in Europe Policy Advisory Group, BiEPAG)」は、一連の論考を通じてこの概念をさらに発展させた。特に、「西バルカンにおける民主主義の危機-スタビリトクラシーの解剖学とEUによる民主主義促進の限界」と題された2017年の報告書は、EUの対西バルカン政策がこの地域における権威主義化の促進要因として機能している状況を克明に描き出し、以降のスタビリトクラシー研究においてはほぼ必ず参照される重要な成果となった。その後もBiEPAGは、EUが安定を過度に優先するあまり、EU加盟交渉において核心であるべきはずの法の支配や民主的な説明責任といった基準の適用を自ら緩めてしまい、結果的に地域の権威主義化を助長しているという「スタビリトクラシーの罠(The Stabilitocracy Trap)」に陥っていると繰り返し警告してきた。
BiEPAGの先駆的な研究成果に続き、欧州的西バルカン(European Western Balkans, EWB)やクリンゲンダールといったシンクタンクがこの概念を用いた分析を行い、その成果を次々に発表していったことで、スタビリトクラシーという概念は西バルカン政治の分析ツールとして定着しつつある。クリンゲンダールが2022年に発表した報告書「EUが西バルカンで促進するのは民主主義かスタビリトクラシーか?」は、過度に技術的なEU加盟プロセスや「法の支配」の定義の曖昧さ、改革を達成しても特定のEU加盟国の拒否権によって適切な報酬が与えられない(例:北マケドニア)等、EU拡大政策の欠陥が西バルカンの権威主義化に繋がっていると指摘している。EWBは「The Time of Stabilitocracy」と題されたドキュメンタリー動画を制作し、西バルカン各国での上映イベントを通じて、この概念を西バルカンの一般市民レベルに浸透させる取り組みを行った。
このように、スタビリトクラシーという用語は、単なるレッテル貼りではなく、西バルカン地域の政治と、それに関与する国際社会、特にEUの政策の構造的欠陥を解明するための重要な分析概念として確立されてきたのである。近年では、ウクライナの戦後復興の文脈においてこの概念を援用する研究も見られており、スタビリトクラシーは西バルカンという地域の枠組を超えた分析ツールへと発展する可能性を秘めている。
2.EUのジレンマ:「拡大のための平和」か「平和のための拡大」か
西バルカンにおけるスタビリトクラシーを理解する上で、最大の外部要因であるEUの役割と、その政策が内包する深刻なジレンマを避けて通ることはできない。公式には、EUはその理念の根幹として、民主主義、法の支配、人権の尊重を掲げている。EU加盟を希望する国は、これらの価値を定めた「コペンハーゲン基準」を完全に満たすことが加盟の前提条件となる。EUは西バルカン諸国に対し、口を開けば「法の支配改革」の重要性を説き、汚職との戦いや司法の独立を要求してきた。これがEUの公式な建前である。
しかし、その実際の行動は、この建前とは大きく乖離してきた。ここで問われるのは、「拡大のための平和か、平和のための拡大か」という根本的な問いである。レトリックの上では、EUは常に前者、すなわち「拡大のための平和」を主張してきた。西バルカン諸国が紛争を乗り越え、善隣関係を築き、国内の平和と安定を確立することは、EU加盟という「拡大」の前提条件である、という論理である。
だが、現実の政策は、後者、すなわち「平和のための拡大」に他ならなかった。つまり、EUにとっての至上命題は、自らの玄関先である西バルカンの「平和と安定」を確保することであり、その目的を達成するための最も強力な「手段(ツール)」が、EU加盟交渉という「拡大」プロセスそのものであった。つまりEUは、「EU加盟」という究極のニンジンを西バルカン諸国の前にぶら下げることで、地域の指導者たちを交渉のテーブルに着かせ、互いに協力させ、少なくとも大規模な紛争が再燃しないようにコントロールしよう苦心してきたのである。
ビーバー等のスタビリトクラシー研究者は、この「手段としての拡大」というEUのアプローチが、結果としてスタビリトクラシーを育て、強化するという皮肉な事態を招いたのだと主張する。彼らによれば、EUが過去10年以上ににわたり行ってきた「安定と価値のトレードオフ」は、西バルカン地域におけるEU加盟の魅力そのものを弱める結果となっている。地域の指導者、特にセルビアのアレクサンダル・ヴチッチ(Aleksandar Vučić)大統領のような巧みな政治家は、このEUのジレンマを完璧に見抜き、最大限に利用した。ヴチッチは、EUが最も重視するのがコソヴォ問題の「管理」、即ち紛争再発の回避であることを理解していた。そのため、コソヴォとの対話において何らかの「進展」を見せるたびに、EUはそれを歓迎し、その見返りとして、セルビア国内で進行する深刻な民主主義の後退やメディア弾圧には目をつぶってきた。例えば、ブリュッセルでの対話でヴチッチ大統領が建設的な姿勢を見せたと評価されれば、その直後に(世界の民主化の進展を評価するNGOとして有名な)フリーダムハウスの報告書でセルビアの民主主義スコアが大きく下落しても、EUは新たな政策分野(章)についてのセルビアとのEU加盟交渉開始を認める、といった対応を繰り返してきた。
これは、EUが自ら定めたはずの加盟基準を事実上、骨抜きにしていることを意味する。法の支配や民主主義といった「価値」よりも、対話の継続という「結果(安定)」が優先される。この構造の中で、地域の指導者たちは「安定の提供者」としての自らの価値を高め、西側からの暗黙の承認を盾に、国内での権威主義的支配を盤石なものにしていった。EUは平和と安定を求めて拡大というツールを使ったはずが、その結果、自らの価値観とは相容れない非民主的な体制を域内に招き入れかねないという、自己矛盾的な罠にはまり込んでいるのである。









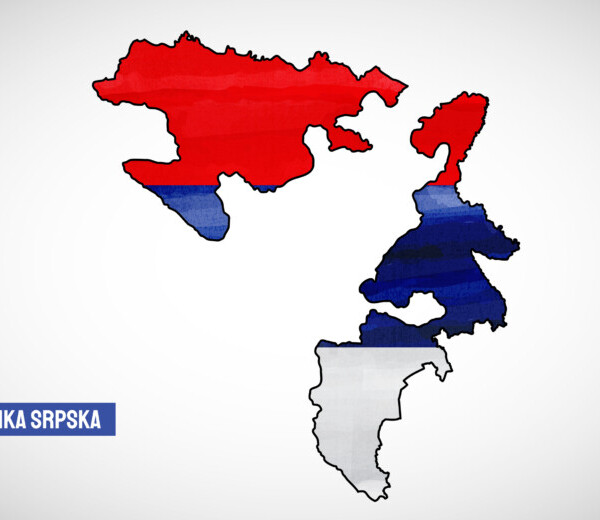














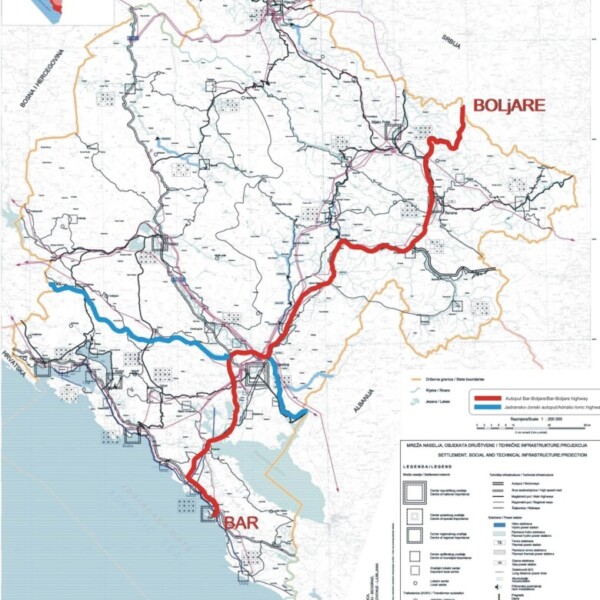




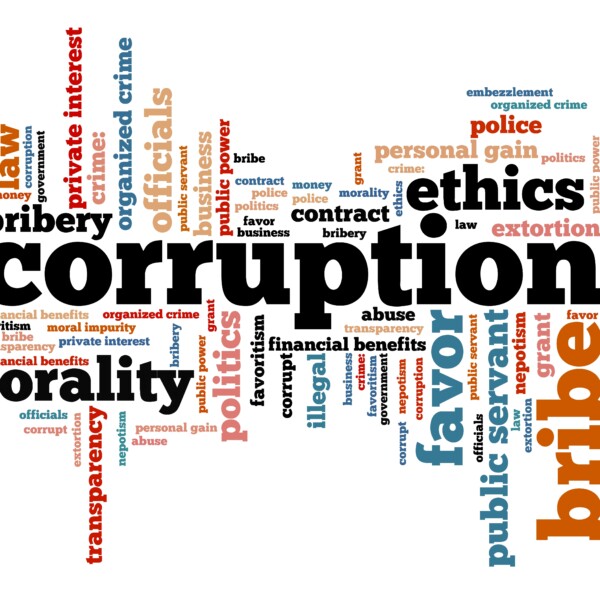






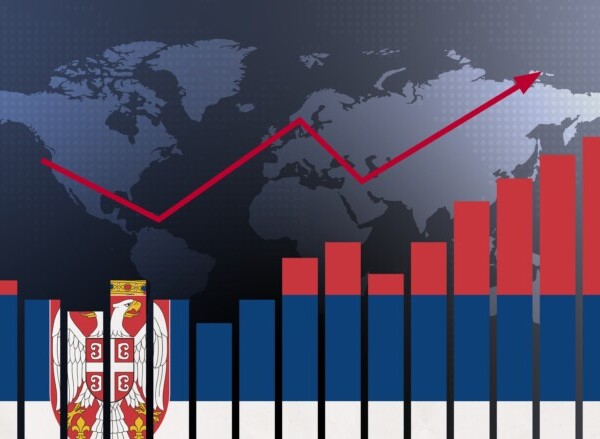






















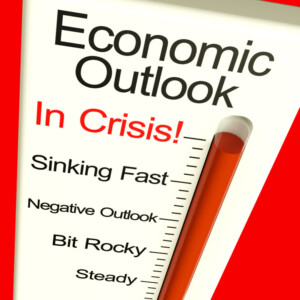







この記事へのコメントはありません。